今回の記事は身長差や手足のサイズ差で悩んだことのあるクライマーのあなたへ向けた記事となっています。
実際の身長差や手足のサイズを具体的な数値として知ることは周囲のクライマーへのアドバイスの際にも役立つと思いますし、話のタネにもなると思います!

普段から一緒に登っているメンバーを思い浮かべながら読んでみて下さい!
今回調べたのは下記の4つ!
- 身長
- 体重
- 手の大きさ
- 足の大きさ
- リーチの長さ
実際にはどれくらいの数値差があるのでしょうか?
気になる数値について調べてみたので、ぜひ最後までご覧ください!
大クライマーと小クライマーの具体的な数値の違い
※低身長と高身長ではなく、大小で区別しているのは身長以外の値にも着目しているためです。
身長
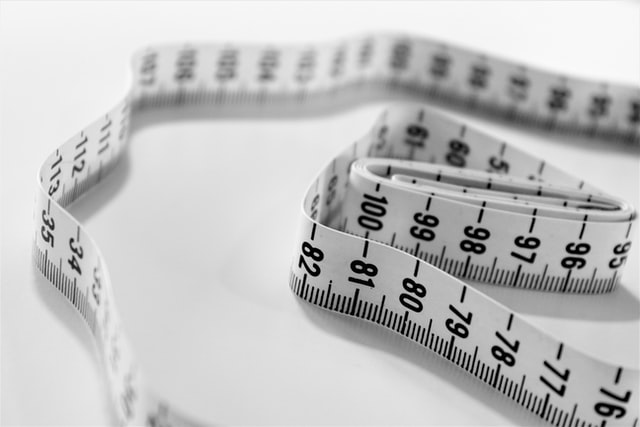
まずは、多くの人が気になっているであろう身長についてです。
身長については令和元年度の政府統計の数値を参考にしてつくらせて頂きました
今回の記事内においては、大クライマーと小クライマーなのかという定義づけのようなものにもなります。
男性平均:167.7cm、標準偏差6.9cm2
女性平均:154.3cm、標準偏差6.7㎝2
日本人の平均身長は上記の値となっていました。
標準偏差の値から男性の場合は167.7±6.9㎝、女性の場合は154.3±6.7cmの間に多くの人が収まっているということになります。
それらの値から抜けている人を今回の記事では大クライマーと小クライマーとします。
大クライマー:174.6cm以上(アダム・オンドラ、楢崎明智)
平均クライマー:167.7cm±6.9㎝(楢崎智亜、村井隆一)
小クライマー:160.8cm以下(是永敬一郎、野村真一郎)
筆者:150㎝
大クライマー:161cm以上(野口啓代、野中生萌)
平均クライマー:154.3cm±6.7㎝(森秋彩、小武芽衣)
小クライマー:147.6cm以下
ちなみに、筆者は身長150㎝なので男性クライマーの中だと頭2つ分くらい抜けた小クライマーということになりそうです。
課題をつくるルートセッターの方々は男性で平均身長くらいの人が多い印象があります。
男性の平均身長である167.7cm±5㎝くらいに収まっているクライマーほどサイズ差による得手不得手は少なくなると言えるでしょう。
数値的に見ると、クライミングジムにある課題のほとんどは女性のリーチでは難しく感じると言えそうです。
男性平均よりも大きなクライマーはちょっと窮屈なムーブを強いられたりすることが多く、それよりも小さいクライマーは距離を感じる課題に出くわすことが多くなります。
体重
体重差もe-statからということにしたいのですが、クライマーは平均値よりも明らかに痩せている人が多いので今回はBMIという考え方を用いて逆算する形で数値化してみたいと思います。
日本肥満学会で適正体重とされているBMI値の22を使用したいところですが、クライマーはそれから1を引いた21で計算してみます。
ちなみに、男性プロクライマーは20前後と言われています。
大クライマー(174.6cm):64.0kg
平均クライマー(167.7cm):59.1kg
小クライマー(160.8cm):54.3kg
筆者(150cm):49kgでBMI値21.8
大クライマー(161㎝):54.4kg
平均クライマー(154.3㎝):50.0kg
小クライマー(147.6㎝):45.8kg
身長を元にBMI値21で体重を求めた場合、上記のような値となることが分かりました。
男性の場合、大クライマーは平均より4.8kg重く、小クライマーは平均より5.2kg軽いということになりました。
大クライマーと小クライマーの差は10kgちょうどです。
女性の場合、大クライマーは平均より4.44kg重く、小クライマーは4.25kg軽いということになりました。
大クライマーと小クライマーの差は約8.7kgです。
体重が1~2kg変わるだけでも保持感はかなり変わるので体重面においては大クライマーがかなり不利、小クライマーはかなり有利に働くということが分かります。
自分のBMI値が気になる方は【BMIと適正体重 – 高精度計算サイト (casio.jp)】で調べてみて下さい。
判定基準は日本と世界で異なります。
- 18.5未満 低体重(痩せ型)
- 18.5〜25未満 普通体重
- 25〜30未満 肥満(1度)
- 30〜35未満 肥満(2度)
- 35〜40未満 肥満(3度)
- 40以上 肥満(4度)
- 16未満 痩せすぎ
- 16.00〜16.99以下 痩せ
- 17.00〜18.49以下 痩せぎみ
- 18.50〜24.99以下 普通体重
- 25.00〜29.99以下 前肥満
- 30.00〜34.99以下 肥満(1度)
- 35.00〜39.99以下 肥満(2度)
- 40.00以上 肥満(3度
手の大きさ

身長ごとの手の大きさは下記の通りとなっています。
これは手首から中指の先までの長さです。
| 身長(cm) | 手の大きさ(㎝) | |
| 標準(基準) | 150 | 16.0 |
| 155 | 16.5 | |
| 160 | 17.0 | |
| 165 | 17.5 | |
| 170 | 18.0 | |
| 175 | 18.5 | |
| 180 | 19.0 |
大クライマー(174.6cm):約18.5㎝
平均クライマー(167.7cm):約17.8㎝
小クライマー(160.8cm):約17㎝
筆者(150cm):17㎝
大クライマー(161㎝):約17㎝
平均クライマー(154.3㎝):約16.5㎝
小クライマー(147.6㎝):約15.8㎝
筆者は150㎝で17.0㎝なので身長の割には大きな手を持っていることになります。
普段の経験からイメージ出来ると思いますが、手が大きいとファットピンチやスローパーに対して強くなり、カチなどの小さなホールドには弱くなります。
逆に手が小さいとカチや小さいホールドに強い傾向があります。
人によってホールドのサイズが変わるなんてことは決してありえません。
小さなホールドは小さい手で、大きなホールドは大きな手で持つなんてことが出来たら最高ですね。
足の大きさ
足の大きさは「身長÷6.7=足のサイズ」というものがあるみたいです。
大クライマー(174.6cm):約26㎝
平均クライマー(167.7cm):約25㎝
小クライマー(160.8cm):約24㎝
筆者(150cm):23㎝
大クライマー(161㎝):約24㎝
平均クライマー(154.3㎝):約23㎝
小クライマー(147.6㎝):約22㎝
こちらも手と同じような理屈でクライミングに影響してきます。
足が大きくて踏みかえるスペースがないというのを実際に見たことがあります。
技術力の向上で対応できる部分ですが、小さいホールドには小さな足が有効というのはあると思います。
逆に、足が大きく体重も重い方が摩擦力が大きくなりボテ踏みは有利という話もありますが筆者の経験的にはあまり変わらない気がします。
荷重出来るかどうかは技術力の方が大きな要因になっていると筆者は考えています。
リーチの長さ
最後は最も話題になるリーチの長さです。
基本的に身長と横リーチ(横に手を伸ばした状態)の長さは同じくらいと言われています。
縦リーチ(上に手を伸ばした状態)は「身長×1.25」で大体の数値が分かるようです。
僕は身長150㎝で横リーチは155㎝、縦リーチ(上に手を伸ばした時の地面から手先までの長さ)は実測188㎝(150×1.25=187.5㎝)なので大体合っています。
大クライマー(174.6cm):横174.6㎝、縦218.3㎝
平均クライマー(167.7cm):横167.7㎝、縦209.6㎝
小クライマー(160.8cm):横160.8㎝、縦201㎝
筆者(150cm):横155㎝、縦188㎝
大クライマー(161㎝):横161㎝、縦201.3㎝
平均クライマー(154.3㎝):横154.3㎝、縦192.9㎝
小クライマー(147.6㎝):横147.6㎝、縦184.5㎝
大体の目安ではありますが、上記のような数値となりました。
男女どちらも小クライマーと大クライマーでは15㎝ほどの差があることが分かりますね。
大クライマーと小クライマーの差を数値で見るとどれくらい?
今までの数値を見て分かったように平均的なクライマーと比較してもそれなりの違いがありましたが、大クライマーと小クライマーの間には下図のような差がありました。
| 身長 | 体重 | 手 | 横リーチ | 縦リーチ | |
| 男性の大小での差 | 約14㎝ | 約10kg | 約1.5㎝ | 約14㎝ | 約17㎝ |
| 女性の大小での差 | 約13㎝ | 約8.7kg | 約1.5㎝ | 約13.5㎝ | 約16㎝ |
記載の小クライマーよりも遥かに小さい筆者だと大クライマーとのリーチ差は20㎝以上になることもあります。
実際の数値で見てみるとかなり差があることが分かりますね。
同じ課題でも登り方や感じ方が大きく変わってくるのも納得といえますね。
この記事を読んでいる方にオススメの記事
まとめ
今回の記事では大クライマーと小クライマーの間のサイズ差についてまとめてみました。
あくまで参考程度ではありますが、今後の登りのスタイルを考えるときにも有効かもしれません。
また、普段から一緒に登っているクライマーに当てはめて考えると面白く見ることができたのではないでしょうか?
ジムに行った際に実際に測りあってみると更に話が広がると思います!
ぜひジムでの会話のタネにしてみてください。
読んで頂きありがとうございました。
次回の更新をお楽しみに!

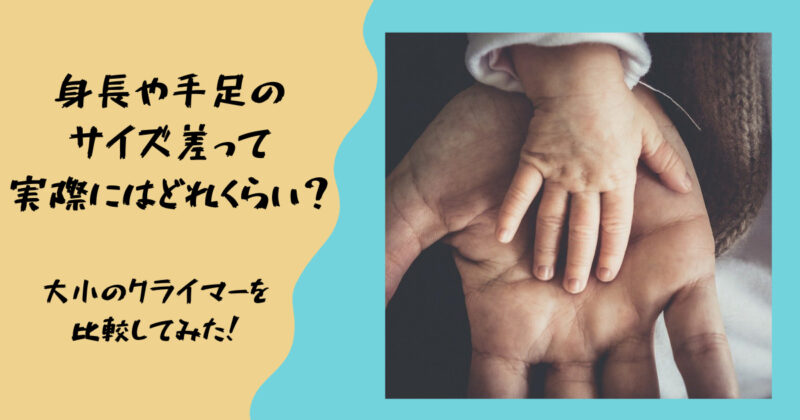



コメント